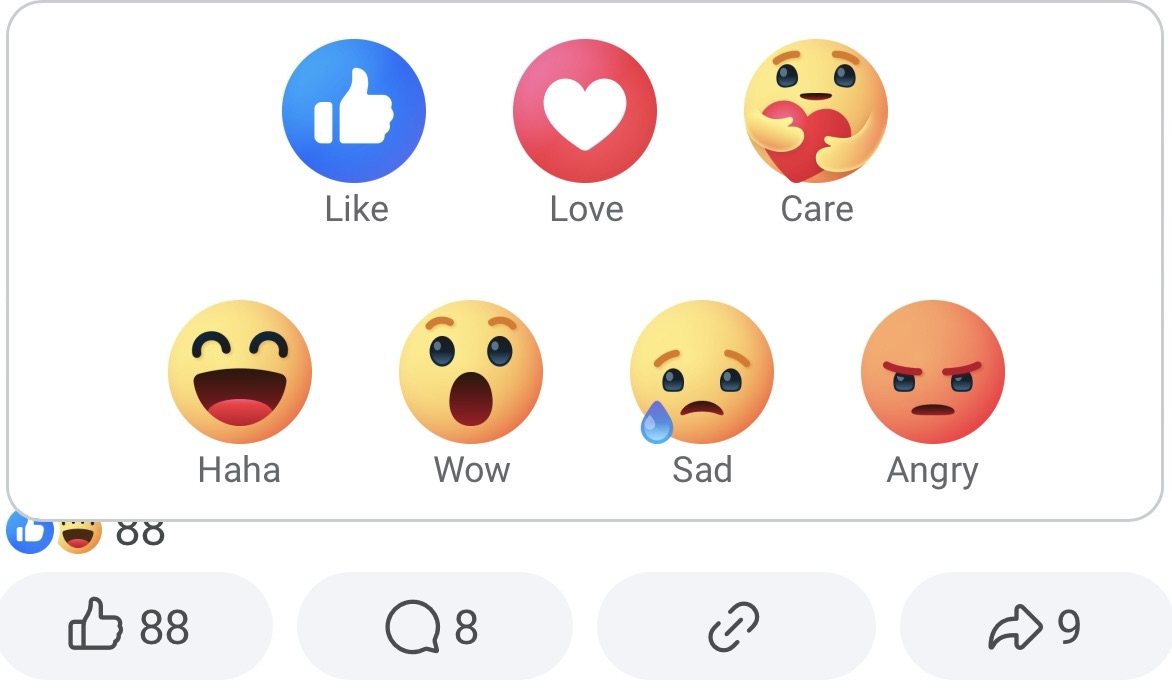韓国では日本製の象印の保温弁当箱が大人気だった。1980〜90年代に学校へ通った者なら、その体躯の手触りや冬の朝に立つ湯気の気配を覚えているはずである。90年代には可愛い白いモデルも見かけたが、記憶の主調はやはり黒である。肩にかかる重みまでが一つの生活感覚であった。
日本で暮らすようになり、中学生の子どもたちの弁当をいくつも用意する日が増えた。寒くなるほどご飯はすぐ冷え、肉の脂は白く固まる。そんなとき象印の保温弁当箱を思い出す。店頭で象印の古風なモデルがまだ売られているのを見つけ、手に取るとサイズはぐっと小さくなっていた。その隣に、いまどきのサーモス(Thermos)のセットがすっきり並んでいた。出自は異なるが、売り場に並べば両者とも日本の生活リズムに合わせて磨かれてきた道具である。
昔は外筒の分解洗浄が難しく、内側の容器だけを洗い、外側は拭うしかなかった。いまの製品はステンレス外装が丸ごと外れ、内部パーツもすべて分解できる。モジュールの着脱で管理が容易になり、食洗機や電子レンジを前提とする設計も増え、衛生への不安が薄れた。保温という性能に、使い心地という体験が合流したのである。
形状も大きく変わった。縦長の円筒を別持ちした時代から、円形の飯容器に四角い副菜容器が横に「ぴたっ」と付く横長の直方体へ。全体の体積は縮み、鞄への出し入れが格段に楽になった。要するに「鞄に収まる設計」への進化である。小さく、しかし的確な改善が日々の摩擦を減らす。
生活道具は不変に見えながら、実は生活の拍子に合わせてゆっくり、しかしかなり徹底して変化する。日本の速度はしばしば遅いと評されるが、その遅さは完成度への執念と対である。設計の意図、洗浄の動線、鞄の実寸まで、細部が軽んじられないのである。
AIもまた同じである。日本の普及は長く鈍いように見えたが、近頃は東京各地でイベントが増え、サービスへ結びつける企業が目に見えて増加している。慎重さは初動を遅らせるが、一度踏み込めば標準を整え、現場のフローを合わせ、リスクを点検する。道のりは長く見えても、進む方角は明瞭である。
今後が興味深い。日本にはアニメやゲーム、キャラクターIPなど制作基盤の厚みがある。ここに生成・編集・管理系のAIが重なり、現場が実際の時間割に合わせて使い始めれば、普及と性能の曲線は急になるだろう。繊細さと几帳面さが「遅さ」ではなく「完成度」へ変換される局面である。
黒い円筒から分離型の横長へ――弁当箱が日常の不便を減らしたように、日本のAIもいずれ「鞄に収まる」かたち、すなわち現場の規格と時間にぴたりと合うかたちを見つけるはずだ。遅いが徹底的な進化は、派手さではなく、納得できる品質として静かに到来するのである。
ソン ウォンソ(Wonsuh Song, Ph.D.)
秀明大学 専任講師 / NKNGO Forum 代表